 第一回 「 忠犬ハチ公の物語 」
第一回 「 忠犬ハチ公の物語 」

※画像は渋谷のハチさんからご提供頂きました。
ハチ公といえば、渋谷駅です。待ち合わせの名所となっている銅像を、思い浮かべることでしょう。
ハチ公のお話は、とても有名です。だれでも、一度は耳にし、本を読んだり、テレビで見たりしたことがあるでしょう。日本人なら――世界においても――みんなが知っている犬の名前です。
さて、みなさんの知っているハチ公の物語とは、どういうものでしょうか。
昔、渋谷駅までご主人を送り迎えするのが日課である犬がおりました。
ところが、ある時ご主人は勤め先で亡くなってしまいました。
犬は、ご主人が死んだとは知らず、駅頭で帰りを待ち続けました。
何年も何年も……死ぬその日まで、待っていました。
これが、よく知られているハチ公のお話のあらましです。
でも、それはいつの時代のことであったのか。待ち続けたご主人はどんな人であったのか。ハチ公という犬は、ほんとうはどういう犬であったのか、あまり詳しい事実は知られていません。
本サイトでは、こうした埋もれた事実を広くみなさんに知ってもらいたいという思いでこしらえました。この講座では、簡単にハチ公の一生をご紹介してゆきたいと思います。
時は、今からさかのぼること、およそ九十年前*。
昭和7年、10月4日の朝日新聞に、次のような記事が掲載されました。
それは、『いとしや老犬物語 今は世になき主人の帰りを 待ち兼ねる七年間』という見出しではじまり、写真つきで一匹の犬を紹介していたのです。
『東横電車の渋谷駅、朝夕真つ黒な乗降客の間に混つて人待ち顔の老犬がある。秋田雑種(※)の当年とつて十一歳の――ハチ公は犬としては高齢だが、大正十五年の三月(※2)に 大切な育ての 親だつた駒場の故上野教授に逝かれてから、ありし日のならはしを続けて雨の日雪の日の七年間をほとんど一日も欠かさず今はかすむ老いの目をみはつて帰らぬ主人をこの駅で待ちつづけてゐるのだ(以下略)』
この日の朝日新聞を目にした人たちは、驚きました。ことに、渋谷界隈の人々の驚きといったらありません。
なぜなら、渋谷界隈では、みんなが毎日のように見ている「駅前の野良犬」であったからです。
新聞で報道されると、もう渋谷駅周辺は大勢の人が押しかけて、たいへんな騒ぎです。みんなが、新聞に出ていた犬を見ようとやってきたのでした。
いつの時代でも「かわいそうなお話」は、世のひとの同情を誘うものです。このときも、たくさんの人たちが、食べ物を持ってきてやったり、撫ぜて慰めてやったりしました。
ハチ公は、一躍駅の人気者です。
今までは、事情を知らない人から、ただの野良犬だと思われ、ときにはけったり、追っ払われたり、いじめられもしたハチ公ですが、有名になるにつれて、駅がだんだん居心地のよい場所となってゆきました。
ところで、このハチ公は、ちゃんと首輪(胴輪)をつけています。畜犬票も持っていました。駅が、ハチ公の身元調査を行いますと、渋谷駅からもほど近い富ヶ谷で、植木屋さんが飼っているということがあきらかになりました。
ハチ公は、野良犬ではなかったのです。
植木屋さんは、小林という名で、菊三郎さんという方がご主人でした。この人は、上野英三郎博士のお宅へ、出入りしていた職人さんです。博士亡きあと、ハチ公を引き取って世話をしていました。
小林さんのお家では、菊三郎さんはじめ、おかみさん、菊三郎さんの弟友吉さん、それから子どもたち、みんながハチを家族のように可愛がっていました。ハチも、小林さん一家の一員として、老年の日々を穏やかに暮らしていました。
この当時、犬は繋いで飼うか、放し飼いにするかが一般的でしたが、小林さんのお家では、ハチが好きに出歩けるようにと、散歩のとき以外は放してありました。
放たれたハチは、吸い寄せられるように、渋谷駅へ行ってしまいます。そして、毎日、改札を出入りする人々を眺めるのがくせでした。
それを、みんなは宿なしの野良犬だと、思い込んでいたのです。
注釈
(※ 秋田雑種……新聞記者の勘違いによる誤報で、後に訂正文が出ました。)
(※2 大正十五年……これも記者の誤報で、実際は後述するように大正十四年のことです。)
*サイト初出時は『七十数年前』とありましたのを、この度『およそ九十年前』に書き改めました。(2024.11.18記録)
 第二回 「 ハチ公はのら犬ではなかった 」
第二回 「 ハチ公はのら犬ではなかった 」

松竹で映画化されたハチ公物語(※)や、2006年*にドラマで放送された作品(※2)をご存じの方は、ハチ公を引き取ったものの、急死してしまう植木屋の「菊さん」なる人物をご記憶でしょう。この「菊さん」のモデルとなっているのが、「小林菊三郎」さんです。
映画やドラマでは植木屋の「菊さん」が急死してしまい、ハチ公は野良犬生活を余儀なくされてしまう、という筋たてになっておりますが、実際の小林さんは天寿を全うされましたし、ハチ公も野良犬にはなっておりません。
小林さんにとって上野先生は、単なる出入り先の主人というだけではありませんでした。植木屋として自立するにあたって、先生のお世話になったのです。また、同じく植木屋の修行をしていた弟の友吉さんの面倒も見ていただきました。小林さん兄弟は、仕事疲れにお食事やお風呂をふるまって貰うほど、上野家とは親密なおつきあいをしており、お屋敷の雑用も任され、いわゆる「男衆」の役目をもしていました。
ハチ公が秋田から送られてきたとき、駅まで受け取りに行ったのも菊三郎さんです。
ドラマではお調子者の職人さんといった風に描かれていた小林さんですが、実際はとても無口な人であったそうです。残された写真をみても、むっつりとした顔をして、とっつきづらそうな雰囲気を感じます。
しかしそれは、お世辞をいって人に媚びたりしない、真面目で誠実な性格も感じさせます。上野先生も、小林さんの実直さを好いていたのでしょう。
責任感の強い小林さんは、上野先生の形見であるハチ公の面倒をよくみてくれました。胃腸の弱いハチのために、食事には一層気を遣い、滋養のある牛肉を食べさせてくれました。毛皮も折りを見ては梳いてやり、散歩も弟の友吉さんと交代で連れ出しました。また、環境の変化にさみしがるハチ公の気をまぎらわせようと、夜のおつかいのお供をさせたりもしました。
上野先生へのご恩返しばかりでなく、ハチ公を家族の一員として、深く愛していた小林さんであったのです。
ハチ公も、小林さん一家の愛情のなかで、静かな余生を送っていました。決して、一般にいわれているような、悲惨な生涯ではなかったのです。しかし、その一方で、ハチ公にはどうしても忘れることができないほど、かなしいことがありました。それはかつての飼い主――ハチ公にとっては「お父さん」である上野先生との死別と、もうひとつ、「お母さん」との生き別れであったのです。
注釈
(※ 松竹の映画……『ハチ公物語』1987年8月1日公開)
(※2 2006年のドラマ……日本テレビ『ドラマ・コンプレックス』枠『伝説の秋田犬 ハチ』2006年1月10日放送。)
*サイト初出時は『近年ドラマで放送』とありましたのを、この度『2006年にドラマで放送』に書き改めました。また『松竹の映画』『ドラマ』の注釈を加えました。(2024.11.18記録)
 第三回 「 上野家に襲いかかった悲劇 」
第三回 「 上野家に襲いかかった悲劇 」

ハチ公のお母さん、それは上野未亡人に他なりません。映画やドラマをご覧になった方は、おそらくこう疑問に思われたことでしょう。
「どうして、上野未亡人はハチ公といっしょに暮らさないのだろう。何故、他所へハチを預けてしまうのだろう」
中には上野夫人が「犬嫌い」なのであろうと考える人もありました。(※)
しかし、上野夫人は、犬が嫌いであったから、ハチと暮らさなかったのではありません。そこには、上野家の悲劇が隠されていました。
上野博士は、長いこと独身を通されてきましたが、後に年の離れた八重子さんとご結婚なさいました。八重子さんは、茶道裏千家の出身でした。ところが、このふたりは祝福されていっしょになったのではありません。実は、八重子さんは内縁の妻で、戸籍に入っていなかったのです。
どうして、上野先生は八重子さんを籍に入れなかったのでしょう。詳しいいきさつは分かっていません。上野先生のご実家は、三重県にあり、地元では名家で知られていました。先生は若い頃に、親の決めた結婚に承服出来ず家出をしたのだ、という話も残されているくらいですから(本当のことかは分かりませんが)、ご実家への遠慮もあったのではないでしょうか(※2)。
子どものなかった上野ご夫婦でありましたが、たくさんの愛犬に囲まれ、家族の絆はしっかりとつながっていました。ハチ公は、こうしたなかで、みんなに愛され、すくすくと成長していったのです。
ところが、突然訪れたのが、大黒柱である上野先生の急死です。
いつものように学校で講義をしていた先生は、脳溢血であっというまもなく世を去られたのでありました。大正十四年の五月二十一日のことです。
音をたてるように、上野家は崩壊しました。残された夫人と愛犬たちは、「たちのき」を迫られたのです。戸籍に入っていない八重子さんは、法的にいっさいの財産を相続する権利を持たないのです。先生亡きあと、お屋敷に住むことさえ許されませんでした。四十九日も待たずに、多くの荷物も持たず借家へ移らねばならない八重子さんは、ハチ公や、その他の愛犬、ジョンやエスたちを、親類のお家へ預けることを余儀なくされました。
注釈
(※ 上野夫人について……戦前に発行された物語では、夫人とハチとの交流をはじめ、夫人が郷里へ帰らねばならないことや、ハチ公がどうしても渋谷から離れられないいきさつを描くことによって、家庭の事情には触れずに『なぜハチ公は渋谷へ残ったのか?』が分かるように記される傾向にあるようです。)
(※2 …当時の法律では、男子満三十歳以上、女子満二十五歳以上であれば自由に結婚が出来ましたが、それ以下の年齢では父母の同意が必要でありました。)
*サイト初出時は『当時の人は、上野夫人が「犬嫌い」なのであろうと考えていました。』とありましたのを、この度『中には上野夫人が「犬嫌い」なのであろうと考える人もありました』に、ほか一部書き改めました。新たに注釈を二つ加えました。(2024.11.18記録)
 第四回 「 あちらへこちらへ転々と 」
第四回 「 あちらへこちらへ転々と 」

ハチ公が最初に預けられたのは、日本橋にある呉服屋さんでした。
ここでは、短い綱につながれたままで、お散歩もできませんでした。無理もありません。呉服屋さんでは、商いが忙しい上に、突然ハチのような大きい犬を任されたのですから、正直なところ、扱いかねたものでしょう。あるとき、お店のお小僧さんがハチの綱を解いてやったところ、大喜びでハチ公はお店のなかに上がりこんでしまいました。丁度お客さんできていた他所の小母さんのうしろ姿を、とっさに「お母さん」と思い込んだハチは、必死になってとびつきました。お客さんにしてみれば、大きな犬に襲われたようなものです。お店は大騒ぎになってしまいました。
お客さんの信用が第一の商店です。この「そそう」から、ハチ公は別の親類の所へ行くことになりました。今度は、浅草の高橋さんというお家で、理髪用の椅子を製造していました。
高橋さんのお家には、Sという名の犬が飼われていました。ハチ公はS君と仲良しになり、並んで写した写真も残されています。食事もよいものを食べさせてもらい、大切に扱われましたが、ハチにとって満足できないのが散歩の問題です。
ご主人の高橋さんや、息子さん、力持ちの文子さんという女中さんが、代わる代わる、時間を見ては連れ出してくれますが、なんといっても育ち盛りの秋田犬が相手です。遊びたい年頃のハチ、まして上野家では広々としたお屋敷の敷地で、のびのびと暮らしていたのですから、ちょっとやそっとでは運動した気になりません。あるとき、息子の孝一郎さんは、雪の日に散歩に出て、いつまでも帰らないとだだをこねるハチに手を焼かされました。また、仕事も忙しいときは、じっくり構って貰えずに、ハチはかなしがりました。
そして、一番の問題は、ハチ公の存在が、近所の人たちに誤解を与えてしまったことです。
ハチ公が、大きい犬であったから。人々は、生意気な犬だといったり、近所の犬をいじめたなぞと悪口をきいたりしました。S君が他所の犬にいじめられて、ハチが怒って吠えますと、それだけでハチが悪いことをしたように、その犬の飼い主が怒り出す始末です。とうとう近所の人々と高橋さんの家とで喧嘩がおきてしまいました。上野夫人は、この上迷惑はかけられないと判断しました。
注釈
※このあたりのいきさつは、林正春編『ハチ公文献集』及び岸一敏『忠犬ハチ公物語』に詳しく書かれています。
 第五回 「 離れていても絆はかたく 」
第五回 「 離れていても絆はかたく 」

ハチと別れた上野夫人は、どうしていたでしょうか。ハチがつらかったように、夫人もまた、つらく苦しい思いをしていました。
かつて楽しい日々を送った上野邸は、別のひとに買い取られ、懐かしい思い出の刻まれた家具は、道具屋へ売り払われました。それを、どうすることも出来ない夫人です。女のひとが一人で暮らしていくのが、とても大変であった時代のことです。夫人は茶道の先生をはじめて、暮らしをたてていました。
そこへ伸びてきた、多くの救いの手がありました。上野先生が大切に育んできた門下生たちです。
門下生たちは、上野先生の別荘――これは先生の死後は門下生の持ち物にするという約束がされていました――を売り払い、夫人の新しいお家を買う資金にあてました。また、売り払われてしまった家財道具を買い戻しました。だれよりも尊敬する先生のために、その奥さんのために、門下生たちは協力しあったのです。
ようやく夫人の新宅が、世田谷に出来上がったのは、年号も昭和と改まっていました。やっと、ハチと暮らせるときがきたのです。夫人がハチを呼び寄せると、ハチの喜びといったらありません。ふたりは、しっかりと抱き合ったことでしょう。
しかし、悲劇はまだ終わってはいなかったのです。
ハチのほかに、上野家で飼われていたエスという犬がありました。かつては、仲良く遊んだ兄弟のような仲です。ところが、どうしたというのでしょう、エスはハチを見るなり威嚇して噛み付いてきたのです。
エスはどこへ預けられ、どんな暮らしをしてきたのか伝えられていませんが、目まぐるしい環境の変化は、エスにとって大きなショックであったに違いありません。まるで犬が変わってしまったようなのです。
ハチをいじめるエス――このままでは、二匹をいっしょにはしておけません。また、散歩の問題も解決されていません。昔のことでありますし、女の人が大型犬を散歩させるのは、難しいのです。結局、あの頃の習いとしては放し飼いにする他ないのですが、ハチ公が畑に入り込んで荒らしてしまうのだと、お百姓さんがカンカンに怒って文句をいいにきました。
夫人は悩みました。亡き夫との思い出をつなぐ、大切なハチ。しかし、このお家にいては充分に散歩もさせてやれず、そのためにお百姓さんを怒らせ……、またエスとの問題……。
悩みに悩んだ上野夫人の心を動かしたのは、懐かしい渋谷の町を恋しがるハチの姿でした。いつまで待っても姿の見えない「お父さん」を呼ぶハチの声。
とうとう、夫人は決断します。渋谷駅にも近い富ヶ谷の、小林菊三郎さんにハチ公を預けることにしたのです。
「大切な上野の形見を預ってほしい」(※)
と、夫人が頼みますと、実直な小林さんは断ります。
「大切な形見を預って、もし間違いでもあったら、いいわけがたちません」
「じゃあ、あげる」
夫人は小林さんにハチを「託した」のです。思い出深い渋谷の町に、先生の面影を追うハチの姿が、あまりにせつなかったのです。
「預ってほしい」と頼まれ、きっぱり断った小林さんですが、ハチが自分の家の犬となった以上、責任と愛情を持って、ハチの世話を引き受けました。小林さんのまごころは、最期までハチを見守り続けたのでした。
上野夫人は、心のなかで小林さんに手をあわせました。
「菊さん、ありがとう……」
夫人もまた、影ながらも、ハチを想っていました。ふたりは離れていても、心の絆はしっかりと結ばれていたのです。
注釈
※上野夫人が小林菊三郎さんにハチ公を託すいきさつは、林正春さんが『ハチ公文献集』の中で菊三郎さんの長男・貞男さんの証言を記録しています。
この講座の中では証言内容を物語風に、初出時より多少言葉づかいを変えて公開しています。
以下は『ハチ公文献』の該当箇所です。
『「上野の大事な形見を預かってくれ」というのに、小林さんが「大事な形見を預かって、もし間違いでもあったら、いいわけが立たない」との返事に「じゃああげる」とハチを渡したのは、博士を懐かしむハチがあまりにせつなかったからである。』(林正春『ハチ公文献集』より引用)
 第六回 「 お父さんのいた頃 」
第六回 「 お父さんのいた頃 」

ところで、ハチ公のもとの飼い主である上野博士とは、どういう人であったのでしょう。
上野英三郎博士は、東京帝国大学、農科大学教授という肩書きを持っており、学界にときめく名誉ある学者です。宮中で催された新年会にも招かれているほどのご身分です。お屋敷は渋谷の大向にありました。たいそう広い敷地で、裏庭には野菜畑がありました。庭木も多く、ことに春になりますと、毎年満開の桜が彩りました。花見の宴も催され、明るい笑い声に満ちていました。この、美しく広々としたお庭で、かつてハチは楽しく遊びまわったものでした。
豊かで、満ち足りた上流階級の生活。それが、ハチの最初に知った暮らしです。
上野先生は、ずいぶんお忙しい人で、大学で講義をするばかりでなく、試験場へ赴いて研究をしたり、地方へ出張されて自ら土木の指揮をとったりと、非常に活躍されました。一方で、お体が病気がちであり、療養も必要とされ、それが奥さまの八重子さんを心配させました。
多忙の上野先生ですが、ハチをはじめとして、ジョンやエスたち愛犬をしっかりと可愛がりました。ことに、ハチは家にきたときから病気ばかりするので、先生は普段から気をつけていました。
お仕事で留守がちの先生に代わって、ハチたちの面倒を見ていたのが、書生の尾関才助さんです。尾関さんは、才ちゃんという愛称で親しまれ、残された写真を見ると、まだ紺絣のよく似合う少年です。先生は、才ちゃんに「犬日記」をつけさせていました。これを読むことで、先生がいない間に起こったことが分るようになっていました。
あるときの「犬日記」には、才ちゃんが子犬のハチと、ジョンを連れて散歩に出たときのことが書かれていました。代々木の練兵場で兵隊さんが演習する鉄砲の音が聞こえると、ハチがいやがってむずがったというのです。
この日の日記を読んだ上野先生と奥さんの間に、次のような会話がされました。
「おや、ハチは鉄砲の音がいやなのだな」*
「そういえば、この間よその子どもらが、前の通りでおもちゃの鉄砲を鳴らしますと、パチンというのを聞くなり、ハチは慌てて座敷へ駆けあがったのですよ」
先生は、さっそく才ちゃんに、ハチをつれておいでと言いました。そして、ハチをだっこして、
「おまえは鉄砲の音がいやなのかい。怖くないのだから安心おし」とあやしてやりました。(岸一敏『忠犬ハチ公物語』参考)
まるで、にんげんの親子のような、一家の団欒でありました。
注釈
※在りし日の上野博士とハチ公の暮らしは、岸一敏さんの『忠犬ハチ公物語』に詳しく書かれています。
*鉄砲の音を怖がるハチ公のことを、上野博士と夫人が話す部分は、同書を参考にしました。
初出時は多少言い回しを変えつつも同書に添っておりましたが、今回(2024年11月)の加筆修正に際して、同書を参考にしつつセリフを独自に書き直しました。
 第七回 「 なつかしい日々 」
第七回 「 なつかしい日々 」

上野先生は、多くの人から信頼され、尊敬された人でした。門下生たちは深く先生を慕っていました。先生は、思いやりの深いお人柄であったといいます。
やさしい上野先生は、ハチの「性格」を受け止め、まっすぐに伸ばしてやろうと考えていました。
書生の才ちゃんが、ビスケットをごほうびに、「おあずけ」や「チンチン」をハチに仕込んでいますと、先生はやんわりと叱ります。
「才助、そんなふうに犬に芸なぞ仕込んではいけないよ。犬が卑しくなってしまうからね」
食べ物につられて、犬が卑しい心持ちになるのを、先生は嫌がったのです。
一方で、先生は愛らしいハチに対して、目にいれても痛くないというほどの、「子煩悩」でありました。
ハチは、子犬のころは、よく先生のベッドでいっしょに寝かされていました。うちへ来てからというもの、体が丈夫でないハチは、しょっちゅうおなかを壊していました。先生は心配で、様子を見るとともに、ハチの体が冷えないようにと注意していたのです。ようやく、元気になって、体も大きくなると、ひとりで眠るようにしつけましたが、ハチはさみしがって、クンクンなきました。先生は、つらかったことでしょうが、ぐっと堪えました。
ところが、明日はおうちでお花見の会が開かれるという日。先生は学校から帰ると、ハチをだっこして話しかけました。
「ハチははじめてのお花見だね。明日はたくさんお客さんがくるのだから、座敷にあがってご挨拶しなさい。さあ、きれいにお化粧しようね」
そして、いっしょにお風呂へ入れてもらいました。先生にきれいに洗われて、それから懐かしいベッドのなかに寝かされたのです。ハチは、どんなにうれしかったことでしょう。
また、こういう日もありました。吹雪の晩のことです。
その頃は、もう外の「犬箱」で寝かされるようになっていたハチは、夜中におしっこがしたくなります。ハチは敷地のなかでは用を足さない習慣がついていましたので、表へ出ようとしますが、上野邸のがっしりとした長屋門は、かんぬきがかけてあって、押しても開かないのです。ハチは、クンクン鳴きました。こういうときは、才ちゃんを起こせばよいのですが、書生部屋は遠い上に吹雪く音で、なかなか気づいてもらえません。とうとうハチは、先生の部屋の前へゆき、雨戸をなきながら揺さぶりました。
すると、先生はすぐに起きてくれたのです。
「ハチ、おなかが痛むのか!もしやご不浄かな?」
先生はハチの素振りを察して、すぐに門を開けてくれました。寝間着で飛び出した先生を追いかけて、奥さまがオーバーを持ってきてくれました。才ちゃんも、慌ててやってきて、気づかなかったことを謝ります。先生は、
「ハチはまだほんの小さな子供だから、手間もかかるだろうが、よく世話してやってくれ給え」
と答えました。この言葉には、ハチを愛するとともに、まだ少年の才ちゃんを気遣う心もこめられていたことでしょう。(岸一敏・「忠犬ハチ公物語」参考)
注釈
※上野邸のお花見や吹雪の晩は、岸一敏さんの『忠犬ハチ公物語』を参考にしました。
初出時は多少言い回しを変えつつも同書に添っておりましたが、今回(2024年11月)の加筆修正に際して、同書を参考にしつつセリフを独自に書き直しました。
 第八回 「 甘えん坊の『忠犬』 」
第八回 「 甘えん坊の『忠犬』 」

「お父さん」と「お母さん」、それから才ちゃんをはじめとする、上野家の人たちに見守られて、ハチはぐんぐん大きくなりました。そして、「ハチ」という個性や性格が育まれてきました。
ハチ公というと、どんなイメージがあるでしょうか。
「忠犬」「恩を忘れない犬」という代名詞や、「かわいそうな犬」という印象が、多くの人に与えられていることでしょう。
どうもハチ公というと、「忠犬」の名にハチ自身の個性が隠されてしまったり、お涙頂戴といった雰囲気になってしまったりいたします。これに対し、本サイトでは「生きたハチ」「ほんとうのハチ」を再現してみたいのです。
そもそも、ハチ公とはどんな「犬格」の持ち主であったのでしょう。
先生の愛情に育まれたハチ公は、結構「甘えっこ」さんであったようです。
たとえば、こんな話も伝えられております。
先生といつも一緒にいたいハチは、来客中でも構わず先生に付きまとい、時にお客さんとの談話の邪魔になることもあったそうです。(上野先生の門下生談※)
ハチは、「お父さんっ子」でした。
ひとりで寝るのが嫌で、くんくん泣いたハチ。お仕事に行く先生を追いかけて、とびついて、だっこや頬ずりを求めるハチ。
先生の体が悪くなって、別荘へ静養に出かけることになると、それと察したハチが、「いっしょに連れて行って!」と甘えます。
先生もきっと、別れをさみしがるハチに、「いっそ、ハチだけでも……」と思ったのではないでしょうか。しかし、先生は、別荘へ遊びに行くのではありません。しっかりと養生してお休みにならなくてはいけないのです。それに、いくらハチがまだ子どもだといっても、ひとりだけ贔屓には出来ないのです。
「いやいや、お前を連れていっては、ジョンやエスも連れていかねばなるまい。かわいそうだが、お留守番をしているんだよ」
先生は、やさしくハチに言い聞かせました。
甘えっこのハチ公、これは裏返すと、「さみしがりや」であったともいえます。
ハチ公が失ったもの。それは単純に上野先生一人ではなかったのです。住み慣れた家や家族、恵まれた幸福な暮らしを失ったのです。
ハチ公を忠犬にしたのは、上野先生の愛情だといわれています。
確かにそうですが、しかし上野先生が生きていたら、少なくとも一家が離れ離れにならなければ、ハチ公は一生、何処にでもいる甘えっこの犬で暮らしたことでしょう。
ハチ公を「忠犬」にせざるを得なかったものは、上野家の悲劇に他ならないのです。
注釈
※上野博士の門下生の証言は、参考元の記事を失念してしまいました。心当たりがある方はご一報ください。
 第九回 「 お父さんはどこに 」
第九回 「 お父さんはどこに 」

「じゃあ、行ってくるよ」
「行ってらっしゃいませ」
上野先生がお仕事に出かけると、そのあとをハチや、ジョンにエスが追いかけます。そして、とびついて、頬をすりよせます。
「こらこら、そんなにしては、歩けないよ」
困った顔をしながらも、にこにこ笑っている先生に、後ろから奥さまが、
「ほら、おいたしちゃいけませんよ。だんな様のお召し物が汚れてしまうでしょう」
と、やさしくたしなめます。
さあ、一、二。一、二。まるで行進するように、先生と犬の一行が門を出ます。ハチがふりかえると、奥さまがいつまでも見送っていました。
これが、上野家の朝でした。
ところが、ある日を境に、みんななくなってしまったのです。懐かしいお屋敷も、毎日通った道も、桜の木も変わらないのに、「お父さん」がいないのです。「お家」に帰れないのです。そして、家族がばらばらになって、「お母さん」とさえ離れ離れになってしまったハチ――。
もし、わたしたちが、同じような目にあったら。忘れることができるでしょうか。幸福であったあの頃を。大好きなひとたちのことを。
例え、静かで穏やかな日々に身を置くことができても。大切な記憶を消すことは出来ないのです。だから、ハチは渋谷駅へ通いつづけたのでしょう。
そこが、上野先生をはじめとする、過去をしのぶ場所であったからではないでしょうか。
ハチは、もとのお屋敷を訪ねることは、ほとんどなかったといいます。今は、別の人が住んでいるのを知っていたからでした。
ほんとうは、先生がもう帰らないことを、ハチは気づいていたのではないか、といわれています。
先生のお葬式の夜、ハチはガラスを押し開けて、部屋へ入ってきました。そして、棺の下に腹ばいになって、どうしても動かなかったと、後に上野未亡人が語っているそうです(※)。
「おや、ハチがあんなところに……」
「出ておいで、ハチ!」
みんながハチを呼びますが、いやがって言うことを聞きません。奥さまが、
「お行儀が悪くてみなさまに失礼ではございますが、どうかあのままにしてやってください。お別れをいいにきたのでしょうから……」
とあいさつをされました。辺りにはしめやかな空気が満ちていました。
ハチは先生の夜具がしまってある物置に入って、三日間、用意されたエサを食べようとしませんでした(※2)。布団をくるんでいる紐を食いちぎると、「お父さん」のにおいがふわっと広がり、脱脂綿と、血のついたシャツが出てきたのです。ハチは、思う存分シャツについた血を舐めました。
いつの間にか、つかれて眠ってしまったハチを起こしたのは、「お母さん」の声です。
「ハチや、こんなところにいたの。ご飯をこの三日というもの食べないというじゃないの!だんな様はね、もう遠い、遠いところへ行ってしまったのだよ……」
ぽたぽたと、ハチの上にあつい涙が降ってきました。
「さあ、早く向こうに行って、ご飯を食べて元気を出すんですよ。ねえハチ――お前もかなしいだろうけど、私だって、とてもかなしくって、この三日ご飯が喉を通らないのだよ……」
「お母さん」は、ハチを抱きしめて、頬ずりをしました。涙がなんべんもハチの背中を濡らしました。(岸一敏・「忠犬ハチ公物語」参考)
注釈
(※告別式の夜のハチについては、
昭和31年8月19日『週間朝日』の中で平岩米吉氏が上野夫人から聞いたとして、
「庭からガラス戸を押し開けて、部屋へ入りこみ、棺の下にはらばいになって動かなかった。上野の夜具を物置に入れると、一しょに入って、どうしても出なくて困った」
と書き残しているのが、林正春さんの『ハチ公文献集』に収録されています。)
(※2 ご飯を食べないハチと夫人のやりとりは、岸一敏さんの『忠犬ハチ公物語』を参考にして書きました。)
 第十回 「 お母さんのにおい 」
第十回 「 お母さんのにおい 」

かなしい別れを経て、小林さんのお家に落ち着いたハチは、お父さんの思い出を求めて渋谷の町を散歩します。
あるとき、ハチは大喜びで駆け出しました。道を歩いている「お母さん」に気がついたのです。後ろからとびつかれて、上野夫人は道路に転びました。
「お母さん」の姿を見つけると、もう夢中になって、まわりが見えなくなってしまうハチです。日本橋に預けられていたときも、上野夫人が会いに来てくれると、必死に甘え、帰るときには心が裂けてしまうような声で泣きました。
綱を解かれたときには、お店のなかに上がりこみ、同じ年頃の他所の奥さんを、「お母さんだ」と思って、抱きついてしまったのです。
ハチ公といえば、上野先生との絆ばかりが強調されてしまいます。上野夫人は、犬嫌いの誤解を受け、なかには、ハチにろくなエサも与えずつらくあたったかの如くいうひともあるようです。しかし、それはとんでもないことです。
もし、上野夫人がそんな人であったら、ハチはこれほどになついたでしょうか。体いっぱいに抱きついて、甘えたでしょうか。
「お母さん」に甘えるハチの姿を、印象的に書き残している文献があります。それは、日本犬保存会創立者・斎藤弘吉さんのご本です。
昭和8年の夏。彫刻家の安藤さんのアトリエに、ハチがモデルとして通っていたときのことです。
連日の暑さに、ぐったりとして元気のないハチ。なかなか良い格好をしてくれません。ところが、ある日、玄関先に女の人が訪ねてきました。
「ごめんください」
この声に、ハチの耳がピンと反応し、がばりと起き上がると、あっという間に玄関へ駆け出して行ったではありませんか。訪ねてきたのは、上野夫人であったのです。
暑さも忘れて、お母さんにじゃれつくハチ公の姿に、安藤さんと、その場に居合わせた斎藤さんは感動します。
「私はハチの一生であの時ほどいじらしいと思ったことはない。」(斎藤弘吉『日本の犬と狼』より)
やがて、ハチはおじいさん犬になり、目もかすみ、耳も少し遠くなりました。駅で、上野夫人と同じ年頃の、ちょっと似たような奥さんを見ると、間違えて寄っていく場面が、当時放送されたラジオの童話劇に描かれています。(※)。
最後の日も近くなった頃、衰えたハチを案じて、上野夫人は駅へ様子を見に行きました。
「ハチや」
と、やさしく呼びかける声も、もうハチの耳には届きませんでした。
右手をそっと出してにおいをかがせると、ようやく分ったと、夫人の言葉が残されています(ハチ公の死亡記事より※2)。
ハチには、「お父さん」とともに、生涯忘れ得ぬ、「お母さんのにおい」であったのです。
注釈
(※ 林正春編『ハチ公文献集』収録、『朝日新聞』昭和九年四月六日JOAK「けふの放送番組」に紹介されたハチ公の童話劇「忠犬ハチ公」の中に、
「(略)ハチ公はよその小母さんを見つけてかけて行きました
小母さんがびつくりしたので、駅長さんはハチ公はもう年が十二……人間なら八十歳位……目や鼻が利かないものですから御主人の奥さまと間違へたのです許して下さい(後略)」
とあります。)
(※2 林正春編『ハチ公文献集』収録、『朝日新聞』三月九日記事より、
「(略)一昨日駅の近くで会ったのが最後となりました、ハチやと呼んでも中々判らず右手を出して匂ひを嗅がせたらやつと判つたらしかった」
と、八重子さんの証言があります。)
 移り変わる時代とともに
移り変わる時代とともに

大正という時代が終わりを告げ、年号は昭和と変わり、やがて秋がやってきました。ハチの、渋谷での生活がはじまります。
この頃、東京は激しい水の流れのように、大きな変化のまっただ中にありました。
ハチが秋田からやってきた頃は、前年に起きた未曾有の大災害・関東大震災の爪あとも生々しく、バラックがあちこちに建っていました。幸い、被害の少なかった渋谷のまちは、家を焼かれた被災者の、救済地にもなっておりました。
東京の都を新しく!これから迎える時代を新しく!
大々的な帝都復興計画のもと、東京は生まれ変わろうとしていました。
人の心も、「現代的」に、「洗練された」「モダーン」な生活を求めていました。断髪に洋装のモダンガールが、軽やかに往来を闊歩しだしたのも、この頃です。
そうした「急げ、急げ」という時代の足音が迫りつつも、渋谷にはまだ昔のにおいが残っていました。「東京府下」である渋谷は、現代の姿がうそのような「田舎」であったのです。
一方で、盛り場はぐんぐんと急成長をみせ、明るい電燈のもと、商店が軒を並べてにぎわいを見せていました。この、まだまだ片田舎ではあるが、これから大いに発展していくであろう「希望のまち」に、ぽつんと現れたのがハチ公であったのです。まさか、一匹の犬によって、渋谷が東京中――いえ、日本中に、そして世界に紹介されることになるとは、まだだれも知る由がありません。
東京が慌しかったように、ハチにとっても、色々なことがありました。新しい小林さんの家では、どんな生活が待っていたでしょうか。
上野夫人は、小林さんにハチの養育費を送ろうとしました。ところが、小林さんはそれを断ります。そして、決して豊かではありませんでしたが、自分たちの力で、ハチ公の面倒をみたのです。
菊三郎さんの弟、友吉さんは、ハチをよく散歩へ連れ出しました。友吉さんとも、古くからの顔馴染みであったハチは、友吉さんによくなついていました。また、ハチを可愛がってくれる近所の人たちもいました。
その内の幾人かを、斎藤弘吉さんも覚えていて、晩年の著書に記しています。
ひとりは、朝日新聞の配達をしていた人で、もうひとりは、駅のガード下の、交番向かい側にあった文具店の店員さんです。配達屋さんは、小林さん一家に代わって、よくハチの散歩をしてくれたそうで、文具店の店員さんは、水を飲ませてくれたりと、ハチを労わっていたといいます。
ところが、このふたりは、不慮の事故で亡くなってしまったそうです。
菊三郎さんと友吉さんで、協力してハチに運動をさせていましたが、植木屋のお仕事も忙しさを増し、散歩を協力してくれた配達屋さんが亡くなると、なかなか思うように時間を割いてやれなくなってきました。これでは、高橋さんのもとで、ハチの味わった散歩の足りない苦しみを、繰り返すことになってしまいます。
あの時代は、現代とは違って、犬の生活もまだ昔のままでしたし、交通量も違います。小林さんはハチが自分で好きに出歩けるように、綱を外してやりました。
すると、ハチは目指すところがあるように毎日出かけてゆくのです。
そこは、懐かしい上野先生を送り迎えした、渋谷駅でありました。
 第十二回 「 渋谷散歩はじまる 」
第十二回 「 渋谷散歩はじまる 」

渋谷駅で乗り降りするひとや、駅の周辺に生活するひとたちは、いつも改札口でぽつんと座っている犬の姿を見かけるようになりました。
「おや、この犬はなんだろう」
あんまり度々目にするので、ふしぎに思うひともありました。
「なんだ野良犬かな」
舌打ちして、早く追っ払えばよいのに、と感じるひともいたでしょう。
あるいは、そこに犬がいることに、さして注意をむけない人たちも、たくさんいたのです。だれも、この犬が何処からやってきて、どういうわけで此処にいるのかを知りません。昭和七年の新聞で紹介されるまで、分らなかったのです。
ふしぎな犬の姿は、渋谷駅だげでなく、駅に通う道すがらにも見ることができました。そこで出会ったひとたちの多くは、この犬がこれから何処へ行こうというのかを知りません。
震災後の、急速に発展していく街のなかでの点にしか過ぎない犬。
ただ、時間だけがこつこつ流れてゆきました。
犬――ハチの渋谷散歩は、すっかりお馴染みになり、仲良しのお友だちもできました。
渋谷駅前に、「梅原園」という製茶の販売店がありました。朝になると、開店の準備がはじまります。店先に台を据えて、品がずんずん並べられてゆきます。忙しく立ち働く店員さんのなかには、まだあどけない顔も見えます。近頃仕事についたばかりの少年です。彼が缶詰の陳列をしていますと、ずんと立ちふさがるものがありました。
仕事の邪魔をするものはと見れば、大きな犬の、ポチンと可愛らしい目がありました。
「あっちへいけ。忙しいんだ」
少年は、犬のお尻を力いっぱい押しのけました。ようやく並べ終わって、一息をいれると、犬はまだこちらを眺めています。
これがハチと、少年店員「吉どん」の出逢いでありました。
ハチは、毎朝吉どんのもとへやってきては、仕事の様子を見ていました。ふたりは、どんどん仲良しになりました。吉どんが、ハチの体をぎゅうっと抱きしめますと、ふわふわとあたたかいぬくもりが伝わってきました。
さて、吉どんと遊んだハチは、とことこと、「梅原園」のお隣にあるお店の前へ歩いてゆきます。もとは魚屋でしたが、いまは「ニカク食堂」というお店にかわっていました。ハチは器用に、前足でドアを、コンコンとノックします。そして、開けて貰ったドアの奥へ入ってゆきました。ここは、ハチが朝ご飯を食べる、ひいきのお店であったのです。
「ニカク食堂」は、残りもののなかから、ハチの好きな食べ物をとっておいてくれました。「ニカク食堂」で食べるご飯――それから食堂の人たちの、そうしたやさしさが大好きなハチは、小林さんちで朝食を食べずに、渋谷駅へ出かけていたといいます。
名前は伝わっていなくとも、ハチの渋谷散歩をやさしく見守ってくれたひとは、他にもたくさんあったことでしょう。
ハチは、先生の思い出だけではなく、渋谷のまちの人情を愛していたに違いありません。
注釈
※「梅原園」の少年店員「吉どん」こと渡辺吉次さんの証言は、林正春さんの『ハチ公文献集』に収められています。
 第十三回 「 庶民のくらしのなかで 」
第十三回 「 庶民のくらしのなかで 」

さて、渋谷駅を逍遥するようになったハチ公の晩年からは、とてもほのぼのとした姿が窺えます。
植木屋の小林さんの家を最後の住処と定められたハチ公は、小林さん一家のまごころと、与えられた自由な時間に、のびのびと暮らしていたようです。
それは、上野先生による、至れり尽くせりの羽毛で包み込むような愛情とは違いますが、小林さんの「ハチのしたいことを認めてやる」という接し方もまた、別の肌触りのする愛情でした。
上野邸での、豊かな暮らしは、幸福そのものでした。ものに不自由せず、そして溢れるような家族の愛。小林さんの家でハチが知ったものは、決して物は豊かでないけれども、毎日を雑草の如く、たくましく生きていく人々の活気と、困った者を助け合う人情でありました。太い、しっかりとした絆でありました。
植木屋小林さんちのハチとして、すっかりご近所とも顔馴染みになりました。小林さんの家に訪ねてきたひとは、玄関前の犬小屋にいるハチに出迎えられました。
お家の裏には、お肉やさんがあります。子どものないご夫婦がやっているお店でした。このおうちでも、ハチはよく可愛がられました。
「ハチ、これはお土産だよ。おうちへ帰ったら、おかみさんに煮て貰いな」
肉屋のおばさんは、肉の包みを風呂敷に入れて、ハチの首へ巻きつけてやりました。
それから、大向小学校の用務員をしているご夫婦も、ハチを労わってくれました。
「ハチや、よっといで。おいしいものを、こさえてやろうね」
高台にあった在りし日の上野邸からは、大向小学校を見下ろすことができました。用務員のご夫婦は、上野家で暮らすハチの姿を、垣根越しによく見ていたのです。きっとご夫婦は、上野先生に甘えるハチの姿を、なんども目にしたことでしょう。
頼りになる巡査さんもいました。
「小林さん、ハチが野良犬捕獲人に捕まったよ。わけをいってあるから、早く行って引き取ってき給え」
そういって、小林さんの家へ飛び込んできたのは、ずんぐりした丸顔の、川上さんという巡査です。近所の、代々木深町交番に勤めていました。
川上巡査は、ハチのことを気をつけてくれて、捕獲人に捕らえられるたびに、助けてくれたのです。川上巡査のおかげで、度々ハチは危ういところから逃れられました。
やがて、渋谷のまちに日が暮れます。
「かえるが、なくから、かアえろッ」
ぽつんぽつんと家に灯がともり、夕焼け雲が流れる頃、ハチは小林さんちの子どもらを、お隣にある銭湯まで送ってゆきました。広々とした「小泉湯」は、小林さん一家が一日のつかれを落とすところです。ハチは、入り口で子どもたちが出てくるのを、じっと待っていました。
「アア、いい湯だったア」
がやがや、楽しそうにみんなが出てくると、ハチもうれしそうに立ち上がります。小さな子なら、背中に乗せて歩くハチです。みんなは、きゃっきゃっと笑いあいながら、お家へ帰りました。お勝手からは、タンタンタン……と包丁のなる音が響いて、おみおつけのにおいが、ふんわりとにおってきました。
注釈
※無名時代のハチ公を気にかけてくれた人々のことは、林正春さんの『ハチ公文献集』に詳しく出ています。
 第十四回 「 変わる東京に夢を追う 」
第十四回 「 変わる東京に夢を追う 」

「昭和」という名とともに、切って落とされた新しい時代は、街の姿も、ひとの心も変えてゆきました。
かつての東京を、詩人の北原白秋はこう唄っています。
金と青との愁夜曲(ノクチユルヌ)
春と夏との二重奏(ドウエツト)
わかい東京に江戸の唄
東京が、まだ頬に血の気さす若者であったとき、昔ながらの江戸の姿が、あちこちに残っていました。しかし、大正十二年に襲いかかった関東大震災によって、古いものはたちどころに失われてしまったのです。代わってにょきにょき現れたのが、時代の先端をゆく、近代都市。洋風の家にビルジングが立ち並び、夜はカッフェーの灯も赤く、若者はジャズに酔いしれました。
「そんなの、ナンセンスよ」
古いしきたりを、鼻で笑って、今時娘は長い髪をジョキジョキ切ってしまったり、くるくるのパーマネントにしてしまい、パリ・モードを気取った洋服に外国香水をふりまくのです。そして、出かけるところといえば、流行のまち「銀座」。「彼氏」の腕を組んで、ハイヒールはダンスホールへと繰り出してゆきます。
昔恋しい銀座の柳……と流行歌「東京行進曲」は失われたかつての柳並木を懐かしみ、「恋の丸ビル」と「ラッシュアワー」のなかで、現代の恋人たちのスタイルを描き出し、「変わる新宿あの武蔵野の月もデパートの屋根に出る」(西城八十 作詞)と、激変する東京の姿を歌いあげました。
お洒落で、夢多き「昭和モダニズム」時代の幕開けです。ひたひたと押し寄せる軍靴の響きを影にして、モダニズムの夢は輝いていました。
こうした時代の変化に、さびしさを感じる人たちもいました。自分たちの知っている東京は、「震災前」という言葉とともに、「古き良き時代」へ遠ざかっていたのです。
かつて東京を愛した文人たちのなかには、都を見捨て、地方都市へ移り住むものもいました。また、モガ・モボ(※1)に代表される若者の風俗に、「まったく近頃の東京人は軽薄になった」と眉根を寄せるひともいます。洋式に変化する生活に、古びた日本を恋しがる世代もありました。
この古きもの、懐かしきものが失われようとする「現代」に、「懐かしい日本」を追いかける人がいました。
名を斎藤弘吉さんといいます。
斎藤さんが求めている「懐かしい日本」、それは昔変わらぬ立ち耳巻き尾をした日本固有の犬たちでありました。
犬好きの斎藤さんは、病気療養中にふとしたことで日本犬に出逢い、その恐るべき減少を知りました。変わっていくのは東京だけではなく、日本という国でありました。日本は、明治の文明開化以来、発展とともに、多くの風習を失いました。固有の動植物もその例外ではありません。ことに、日本犬の雑種化は著しく、もはや東京で立ち耳巻き尾の犬を見ることは難しいとまでいわれていました(※2)。
このままでは、日本固有の犬が滅んでしまう!
斎藤さんは、たったひとりで「日本犬保存会」を発足させました。ときは、昭和三年の五月。その翌々月に運命の出逢いが斎藤さんを待ち構えていました。
注釈
※1 モガ・モボ…関東大震災以降大正の終わろうとする頃に「モダン・ガール」「モダン・ボーイ」という若者の風俗が登場しました。これまでの淑女・紳士とは違って、新しい時代の考えかたやファッションをした若者たちで、ことに女性は当時珍しかった洋装を身に着け、髪の毛を短くオカッパにカットするのが最新流行であったのです。一方でこうした風俗は「軽薄な男女」の象徴ともされ、人々からは冷やかしや白い眼でもって迎えられもしました。言葉として登場したのは大正15年頃とされ、主に昭和初期の代表的な風俗現象でありました。
※2…現在では考えられぬ話ですが、明治大正は日本犬にとって不遇の時代でありました。西洋から輸入された犬ばかり持てはやされ、日本犬は次第に姿を消していったのです。大正期に於いては、犬の絵といえば耳の垂れた洋犬――多くはポインターやセターが描かれるのが定番でした。
昭和初期に入って日本犬がようやく注目を集めだしたものの、まだ柴犬さえも珍しく、一般家庭で飼うのはなかなか難しいと考えられていました。
 第十五回 「 運命は停留所に 」
第十五回 「 運命は停留所に 」

日本犬保存会――という立派な名はついても、活動するのは斎藤さんひとりです。まず、なにからはじめたものでしょう。日本犬を探し出すことです。そして、犬籍簿をつくるのです。どこのだれの飼っている何号と登録します。そうすれば交配をする際も、簡単に相手の犬を見つけることができます。日本犬の血を次へ残すことが出来るのです。
斎藤さんの日本犬探しがはじまりました。
新聞に、立ち耳巻き尾の犬を見つけたら教えてくれるように投書しました。また、自分でも方々を歩き回りました。東京にも、地方から持ち込まれた日本犬が数少ないながらもいたのです。更に斎藤さんの足は、山里までも伸びてゆきます。
ところが、すぐ近くに運命は転がっていました。
七月のある日。バスに乗って外を眺めていた斎藤さんの目に飛び込んできたのは、大きな秋田犬が停留所で遊んでいる姿。慌ててバスを降り犬に近づきました。ところが、犬はびっくりして逃げてしまいます。追いかけて、どこかのお家に辿りつきました。のそっと出てきたおやじさんに、斎藤さんはわけを話します。
「私は日本犬を探している者なんですが、この犬はお宅の犬ですか」
「そうです」
「名はなんというのですか」
「ハチといいます」
むっつり顔のおやじさんは、小林菊三郎さんです。斎藤さんはハチのかなしいいきさつを聞かされ、深く感じ入りました。そして、ハチの名はそのいわれとともに、第一回日本犬犬籍簿に記されました。これが、ハチの記録としては最初のものです。
斎藤さんは、日本犬保存の活動の傍ら、ハチのもとを訪ねるようになりました。ハチに会うには、渋谷駅へ行けばよいのです。
「さあ、ハチ。やきとりでも食おうか」
斎藤さんが屋台でやきとりを買ってきてやると、ハチは喜びました。
「ハチ、おまわりおまわり」
斎藤さんの声に、ハチはくるん、くるんと回ってみせます。芸のきらいな上野先生が教えてくれた、数少ないハチの芸当でした。
「よしよし、よくできたね」
頭を撫ぜてやると、ハチは可愛らしい目でこちらを見つめているのでした。
こうして、折々渋谷駅へハチの様子を見に行く斎藤さんですが、あるときはおやと目を見張りました。
「どうした、ハチ!首輪がないじゃないか。これじゃ野良犬と間違われて、捕獲人に連れていかれてしまう。ああ、また盗まれたんだな。ハチ、お前があんまりおとなしいから――」
首輪だけではありません。畜犬票を安産のお守りといって抜いてゆくひともありました。ハチはなにをされても、決して抵抗しないのです。吠えもせず、唸りもしません。ただ、あの可愛らしいぽっちりした目を丸くしているばかり。
いじわるな人が、ハチをいじめることもありました。
「やい、くそ犬向こうへ行けッ。商売の邪魔だい」
屋台のおやじは、ハチがちょっと側へ寄っただけで、怒って水をかけました。
「チョッ、何処の野良犬だい。いつもここにいやがらア」
通りすがりの人が悪口を吐き捨てていくこともありました。
いつものように斎藤さんが渋谷駅へハチを見舞いに行くと、丁度駅員の部屋からのっそり出てくるところでした。
「おお、ハチ」
思わずふきだした斎藤さんです。まあ、ハチは墨で黒々とメガネを描かれ、八の字髭をつけられているではありませんか。ハチはらくがきされたのも知らずに、悠々と歩いてきます。笑ってしまった斎藤さんも、今度はハチに対する哀れさがわきあがってきました。
かわいそうなハチ!近頃は人情も薄くなってしまった。せっかくハチの好きな渋谷がこんなでは、あんまり不憫だ。みんなが、ハチのことを分ってくれたら……。
斎藤さんは、日本犬保存会で発行していた会誌に、ハチのことを書きました。少しでも多くのひとに、ハチという犬がいることを知って貰いたかったのです。けれども、会誌では読者が限られてしまいます。
そうだ、新聞に投書しよう!
さっそく、朝日新聞にハチのことを書いて出しました。どういう結果になるでしょう?どきどきと知らせを待つ斎藤さんは、ある日新聞を開いて驚きました。
「いとしや老犬物語 今は世になき主人を 待ちかねる七年間」
ハチが写真入りの三段見出しで紹介されていたのです。
こうしてお話は、冒頭の昭和七年に戻ります。
 第十六回 「 新東京名所案内 」
第十六回 「 新東京名所案内 」

ボシュッ、ボシュッ――
「一つ目のお化け」が、大きな音といっしょに光を放ったので、ハチ公はびっくりしてしまいました。それは、ハチの大嫌いなかみなりに似ています。新聞社の写真班がハチを取り囲み、写真を写しているのです。
驚いたのは、ハチだけではありません。渋谷駅の駅員や、駅長までが何事かと目を見開きました。
七日の新聞に記事が出たハチ公は、「秋田雑種」と報道されました。これに、斎藤弘吉さんは抗議文を送ったのです。
「ハチは、れっきとした日本犬です。純粋の秋田犬です」
新聞社ではすぐに訂正文が出ました。これが却って人々の目をひき、ハチの名を広める結果となりました。渋谷駅には、新聞を読んだ人たちが集ってきました。
「あ、あれがハチ公?」
「まあ、大きな犬ねえ」
「咬まないかしら」
がやがやとざわめきがハチを包みます。
「駅員さん、ハチ公に肉を持ってきてやったので、食べさせてもいいですか」
「ハチ公はパンを食べるでしょうか」
食べ物を持ってきた人もありました。
「ハチ公、おまえは偉いんだねえ!」
「よしよし」
「おりこうだね」
子どもたちが、みんなでハチを撫ぜてゆきます。そうかと思えば、紳士が現れ、
「私は獣医をしている者です。新聞を見て、心配でやってきました。是非、無料でハチ公の健康診断をさせていただきたいと思います」
さあ、渋谷駅は大騒ぎです。今まで、ハチをいじめていた人までもが、急ににこにこ笑って、ハチにお愛想をしました。これにはさすがのハチも、ちょっと気味が悪かったことでしょう。
あっという間にハチはみんなの人気者になってしまいました。
地元の商店街では、ハチ公の人気にあやかって、色々な「渋谷名物」を売り出すようになりました。当時の記録によると、「ハチ公チョコレート」、「ハチ公焼き」、「ハチ公せんべい」といったお菓子のほか、ハチ公の人形や、ハチ公プロマイド、はてはハチ公浴衣なんていうものまであったそうです。
さいしょにハチ公美談を報じたのは朝日新聞でしたが、やがて他誌も競って報道するようになり、雑誌にも紹介されたり、ラジオ放送で流れるようにもなりました。
もはや、ハチ公は「渋谷のアイドル」ではなく、「みんなのアイドル」となっていました。日本中にハチ公の名は響き渡り、渋谷は新東京名所となったのです。
「あ、あれがハチ公ね」
自動車に乗って、わざわざ見物に来る人も少なくありません。外国の日本案内記にも渋谷駅のハチ公は紹介されるようになっていました。
 第十七回 「 ハチ公は日本犬広報係 」
第十七回 「 ハチ公は日本犬広報係 」

あれよあれよと有名になってしまったハチ公ですが、ただ人気に踊らされていたわけではありません。ハチ公は、大きな貢献をしていたのです。
それは、ハチ公を最初に紹介した斎藤弘吉さんの活動――日本犬保存運動。
斎藤さんがひとりで設立した日本犬保存会も、やがて同志が集り、本格的な活動が行われるようになりました。ハチ公のふるさとからは、秋田犬保存会が加わり、山梨県からは甲斐犬愛護会が入会し、各地の日本犬愛好家が集りました。守るべき種や、志す道はそれぞれにありましたろうが、目的はひとつ、「絶やされぬ日本の犬を、次の時代へ」――。
そして、いよいよ、昭和七年十一月六日、日本初、日本犬展覧会が催されることになりました。この頃、日本の畜犬界はまだまだ発展途上の揺籃期にありました。幾つかの洋犬種の愛好倶楽部が発足されているばかり。犬の展覧会というのも、まだ珍しかったのです。まして、日本犬が一堂に集められるなど、前代未聞のこと。更に、注目すべきことは、展覧会にわれらが忠犬ハチ公も出席するというのですから、普段犬に関心のない人たちにも、強い印象を与えました。
松屋デパートの屋上で開催された日本犬展覧会には、北は北海道から、南は九州まで、約百頭近くの犬たちが集りました。この内、日本犬保存会により、二頭の犬が特別に招待されました。日本犬のお手本となるような素晴らしい犬と、保存運動に功績のあった犬とを選んだのです。一頭は、伏見宮家で愛育されていた胡麻(ごま)号という秋田犬です。もう一頭が、「渋谷駅の犬」と出陳の備考欄に記された、ハチ公でありました。
当時の日本犬保存会会誌では、次のように記しています。
「(略)此処に功績あるものとして最初に招待したものが、老犬ハチ号なのである。
之も亦秋田の牡である。(中略)故上野博士未亡人及飼養者の小林菊三郎氏が本会の請を受けて、ハチ老犬最初の展覧会出陳を快諾せられ、而も渋谷駅に旧主を慕ふ名物犬に相応しく、美しく清く装はれた事は特にうれしく、会場内に於いても実に懐かしみある人気を一身に集めて居た様子は老犬の徳とでも讃ふ可きかと思はれた。」
(「日本犬保存会50年史」収録の、昭和七年会誌『日本犬』より)
わざわざハチ公を目当てで来た人もありました。斎藤さんも、小林さん、上野未亡人も、みんな今日の晴れの日がうれしくてなりませんでした。
「最初は自動車にもなかなか乗らなくて、どうなることかと思いましたよ」
と、小林さんが朝の一騒動(※1)を話せば、
「ほんとうに、会場でむずがってはと心配していましたが、こんなにおとなしくしているので、ほっとしました」
上野夫人も胸をなでおろし、
「おや、ハチ公へ歌を寄せてくれた人がいる」
斎藤さんは短冊を見つけて読み上げました。
亡き主の帰りますかと夕な夕な
渋谷の駅に老犬の待つ
名前は、石谷嵯峨という雅号があるばかりでした。
「残念だな。何処のだれか分れば、ハチ公の写真でもお礼に贈りたいのに」(※2)
ハチ公がたくさんの人たちに可愛がられるのが、我が事のようにうれしい斎藤さんでした。
日本犬展覧会はなかなかの盛況でした。今まで、地の犬と蔑まれ、洋犬種に押されてばかりいた日本犬は、ハチ公の名とともに、知れ渡るようになりました。
ハチ公の存在は、日本犬保存運動のキャンペーンマスコットでもあったのです。
「ハチ公のような犬を飼ってみたいな」
という思いはやがて、
「ハチ公みたいな秋田犬を飼いたい」
「忠実だという日本犬を愛犬にしたい」
と思う人たちを増やしました。
秋田県大館では、秋田犬を譲ってほしいという問い合わせが殺到したといいます。これを苦々しく感じる愛好家も少なくありません。
「秋田犬は天然記念物です。種の保存をはかるのが先決のときに、そう軽々しく他所へ流出されては困ります。まして、全ての犬がハチ公のようになるとは限りません。ハチ公は上野先生あっての忠犬なのです」
この時代、日本犬の成犬は千円(※3)もの高値で取引されました。良血統の洋犬種の値段にひけを取りません。日本犬の価値は急速に上がっていました。
注釈
(※1 展覧会当日、小林さんが車にハチ公を乗せるまでの一苦労は、岸一敏さんの『ハチ公物語』に詳しく書かれています。)
(※2 『ハチ公文献集』収録中、斎藤さんの当日の感想が『日本犬』に展覧会偶感として書かれているのを参考に、物語風に表現しました。)
(※3 犬の値段 …参考までに週間朝日編『値段史年表 明治大正昭和』から昭和八年の物価を見てみますと、
鶏卵・二十一錢 豆腐・五銭、東京市電乗車賃(全線)・十錢(昭和七年)、銀行の初任給・七十円、都知事の給料・五千三百五十円とあります。)
※第17回以降は未完です。現在準備中のサイトでは公開できるよう頑張ります。
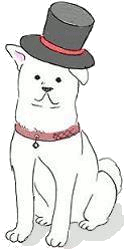
![]() ハチ公ってどんな犬?
ハチ公ってどんな犬?![]() 第一回 「 忠犬ハチ公の物語 」
第一回 「 忠犬ハチ公の物語 」![]() 第二回 「 ハチ公はのら犬ではなかった 」
第二回 「 ハチ公はのら犬ではなかった 」![]() 第三回 「 上野家に襲いかかった悲劇 」
第三回 「 上野家に襲いかかった悲劇 」![]() 第四回 「 あちらへこちらへ転々と 」
第四回 「 あちらへこちらへ転々と 」![]() 第五回 「 離れていても絆はかたく 」
第五回 「 離れていても絆はかたく 」![]() 幸せだった時代
幸せだった時代![]() 第六回 「 お父さんのいた頃 」
第六回 「 お父さんのいた頃 」![]() 第七回 「 なつかしい日々 」
第七回 「 なつかしい日々 」![]() 第八回 「 甘えん坊の『忠犬』 」
第八回 「 甘えん坊の『忠犬』 」![]() 第九回 「 お父さんはどこに 」
第九回 「 お父さんはどこに 」![]() 第十回 「 お母さんのにおい 」
第十回 「 お母さんのにおい 」![]() 時代の中のハチ公
時代の中のハチ公![]() 第十一回 「 移り変わる時代とともに 」
第十一回 「 移り変わる時代とともに 」![]() 第十二回 「 渋谷散歩はじまる 」
第十二回 「 渋谷散歩はじまる 」![]() 第十三回 「 庶民のくらしのなかで 」
第十三回 「 庶民のくらしのなかで 」![]() 第十四回 「 変わる東京に夢を追う 」
第十四回 「 変わる東京に夢を追う 」![]() 第十五回 「 運命は停留所に 」
第十五回 「 運命は停留所に 」![]() ハチ公はみんなの人気者
ハチ公はみんなの人気者![]() 第十六回 「 新東京名所案内 」
第十六回 「 新東京名所案内 」![]() 第十七回 「 ハチ公は日本犬広報係 」
第十七回 「 ハチ公は日本犬広報係 」![]() さよならハチ公……
さよならハチ公……![]() 「 ハチ公の死 」
「 ハチ公の死 」



